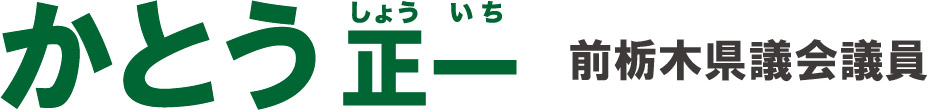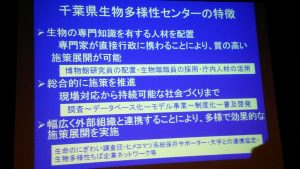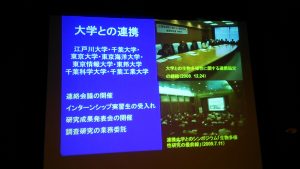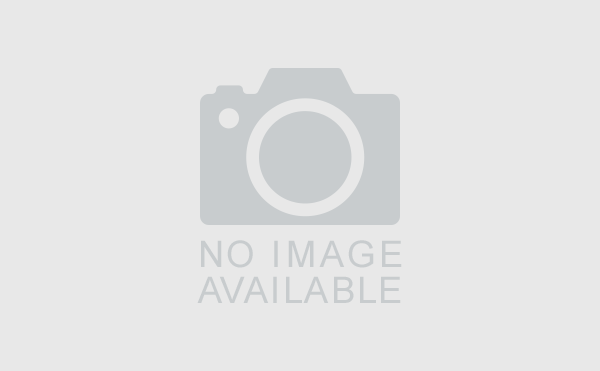県内で絶滅の恐れがある野生動植物等について掲載したレッドリストは平成16年8月策定され、自然環境の現状を明らかにし、広く周知しながら保全の必要性と保護に努めてきました。
23年3月の第2次版を経て県は今年3月、第3次となる県版レッドリストを6年ぶりに改訂。今回の動植物等レッドリスト掲載数は、138種増加し1,531種となり、絶滅危惧種は75種増加し1,021種に上る。新たに絶滅危惧種としてBランクへ引上げられたヤマコウモリ・キンブナ・ニッコウイワナ、湿地の乾燥化・渇水など生息環境の変化からCランクになったアズマヒキガエルやクロサンショウウオ。
平成25年佐野市で約80年ぶりに発見され、2年後茂木町でも採集されたホンゴウソウが絶滅からAランクに変わる中、オナモミは進入外来種の影響で、Aランクから絶滅へと引き上げられた。レッドリスト改訂に伴い掲載種を解説した「レッドデータブックとちぎ2018」を来年3月に発行予定。
これら動向を踏まえ、県民と連携し生物多様性の調査・保全と啓発活動に取組む千葉県生物多様性センターを視察。平成10年環境省設置以降、20年4月に都道府県で最初に千葉県が設置したセンターの概要について熊谷宏尚職員から説明頂いた。
環境省や他自治体が出先機関・研究機関とする一方、本庁組織として自然環境課内に位置付け、執務室を県立中央博物館に置く。データの収集・蓄積及び啓発活動、絶滅危惧種の保全・外来種の防除事業を中央博物館研究員併任の4名含む11名行う。専門知識を有する人材の確保から、公募制による庁内人材活用や生物職職員の採用、任期付又は嘱託職員の活用を図り、現在林業職1・生物職3・一般行政1・文化財4(博物館併任)・嘱託2名で構成。
地理情報システムを活用したデータは約129万件を有し、レッドデータブック改訂に反映する一方、特定外来生物の情報もHPで提供。絶滅危惧種対策では本県でも知られるミヤコタナゴやシャープゲンゴロウモドキ、ヒメコマツなどの回復事業に取組む一方、外来生物カミツキガメの防除に際し市町村・NPO等への支援を行う。
また、県民参加の生物モニタリング活動として「生命のにぎわい調査団」を組織し、調査対象57種について本年3月現在1,235名の団員から81,908件の報告が寄せられている。
これらデータの蓄積に基づき開発事業の指導・保全措置に関する相談や、大学・企業との連携による動植物の多様性保全に向けた啓発活動を行っています。