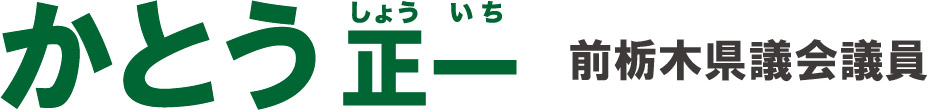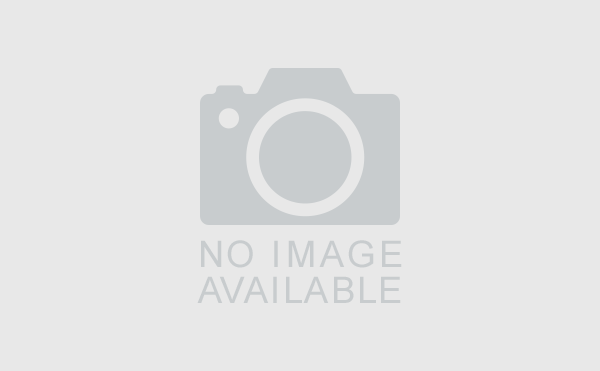今年3月、総務省がIoTやビッグデータなどICT(情報通信技術)の積極的な活用に向け、官民・大学での先進事例を表彰し「ICT社会の深化」を推奨する「地域ICTサミット」について紹介しました。
県議会県政経営委員会では6月20日(火)、佐野日大高校・中等教育学校のICT教育について現地調査を実施。
佐野日本大学学園浦田奨(すすむ)理事長及び渡邊明男高等学校長から、「佐日」の名称で知れる同校が、既に3万人を超える卒業生を送り出す歴史と広いネットワークを有すること、校訓の一つである〔自主創造〕の精神に富んだ有為な人材育成へと、グローバル教育やICTを活用した教育に力を注いできた経緯等伺った。
続いて、ICT教育の環境整備を担う安藤昇推進室長よりインフラ整備とシステムの概要に関し説明頂いた。1990年から取組まれたICT化は雷の影響を避け光ケーブルを敷設し、クリーンルームのサーバー室設置、。コアスイッチとの接続を1Gbpsと想定し、1教室を約50Mbpsで束ねて1棟あたり20教室の授業で利用可能に設計された。Web認証により一人1接続で冗長化が図られ、2,000人同時接続でも支障がないとのこと。
強固なインフラ整備により、校内で動画が自由に閲覧できる環境とデジタルキャンパスを構築。Webサイトや教職員グループウェア、生徒用教育支援システムのもと140万ファイルを生徒と教職員が共有している。
学校情報の周知に加え、部活動も盛んな同校では学校を休んだ生徒に授業の動画や板書を送ったり、テスト終了後には解答を即座に生徒へシエアするなど従来の授業形態を変える取組みです。機器やシステムの利用方法は、タブレットを通じ動画での紹介や校内での研修会を用意。
当日は高校1年の英語授業を参観し、生徒がタブレットにより英訳解答したものを、教師の端末で確認するノートレス形式。ネイティブスピーカーである先生は、生徒がタブレットに向かって話す英語の発音もチェックし授業を進めます。
同校におけるICTのインフラ環境整備には約1億2千6百万円を要し、その内国庫補助金2千6百万円が充当されています。