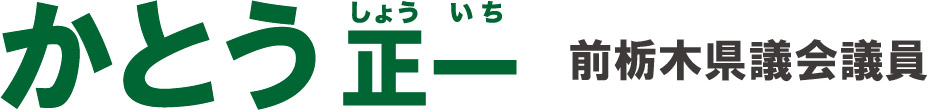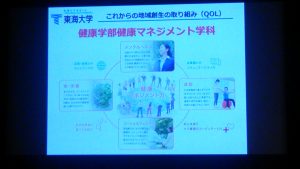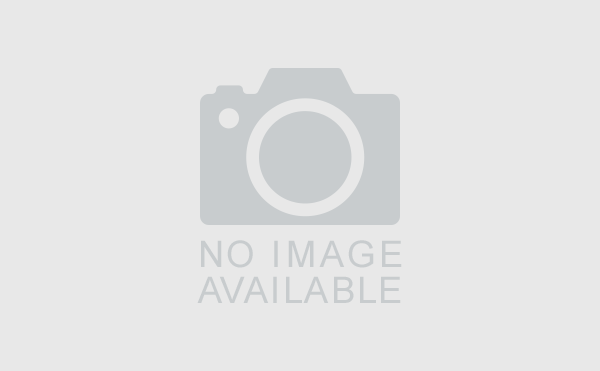県版総合戦略“とちぎ15戦略”のもと、本県取組が3年目を迎えるも、県人口の減少や首都圏への転出超過に歯止めがかからない中、県は課題解決に向けた次年度取組の実施方針を策定した。
成果指標(KPI)の進捗状況等を踏まえ、県内企業のIoT等活用促進や関西圏への観光情報の発信力強化、インターンシップ導入企業の掘り起しなどによる県内企業の人材確保等13の課題を掲げ、農産物の輸出額や観光消費額、本県への年間就職者数など6つの成果指標について、更なる高みを目指して目標値を引き上げ、各種支援策を新年度予算で措置する。
先般、全国での地方創生取組を定期的に紹介する日経フォーラムに参加してきた。テーマはスポーツを通じた取組や企業・大学が実現する地方創生など、自治体と連携した具体的事例を紹介。
梶山弘志内閣府担当大臣から地方大学の支援制度創設やCCRC、農地や空き店舗等遊休資産の活用とともに更なる国機関の地方移転推進が示された。
山崎俊巳内閣府まち・ひと・しごと創生本部事務局次長は、44県で企業版ふるさと納税活用計画があり、都心部や地方の商業地、郊外の住宅地など特定のエリアを単位に、民主導又は官民協働型でまちづくりを行う「日本版BID(business improvement district)」の実践が期待される地域経済牽引企業が2,000社に上ると報告。
また、環境や地域の課題に取組むことで企業の社会的責任を果たす活動CSR(corporate social responsibility)については387事業1,760件が提案され、秋田県の白神山地や群馬県の尾瀬地域の保全、夕張市のコンパクトシティづくり等様々な事業が予定されている。
続いて、チャレンジセンターを設置し地域との共生社会に資する人材育成に取組む東海大学は、今年4月75周年を迎え地域連携センターを立上げ「知の拠点」事業に着手。4つのプログラムによるパブリックアチーブメント教育を、来年から4単位の必修科目とする。合わせて「文化社会学部」「健康学部」を新設し、健康学部には健康について万遍なく学ぶマネジメント学科を設け、協力自治体と住民の健康状態を継続調査し、データを施策の具体化に提供。
官・民・地域が連携し、具体的事例から考える持続可能な経済循環へと、いよいよ地方創生も実装段階に入った!