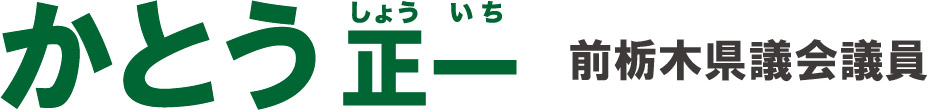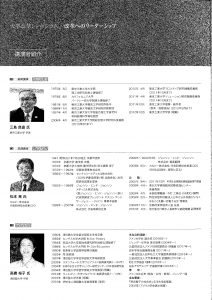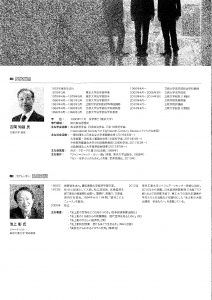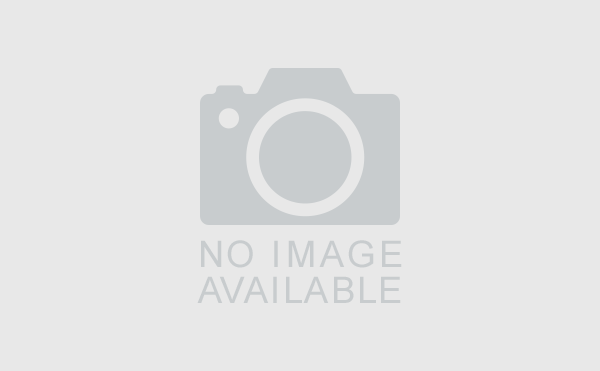政府は昨年6月閣議決定した「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」において「都内大学の収容力が高いため、このまま定員増が進むと地方大の経営悪化や撤退を招きかねない」、「若者の東京一極集中に歯止めをかけ、地方創生につなげる」として「23区内の定員増原則禁止」を打ち出した。
これにより文科省は2018年度の定員増と、翌年度の大学設置を認可しないと告示。更に20年度以降は定員増を法律で禁止する方向とのこと。今年度23区内に学生は46万人が在籍し10年で18%増加、全国で学ぶ学生数の20%を占める。
一方、日本私大連盟や都は「学ぶ機会の自由制約」、「東京一極集中と学生数抑制の関連性への疑義」などの反発から、私大連は「短期間の一時的措置にすること」との声明を出した。
政府は来年度予算において、地方大学振興策として首長が主宰する産学官連携推進体制で地域の専門人材育成、産業振興計画を策定し、有識者会議が認定した優れた事業へ交付金を支給する「地方大学・地域産業創生交付金」を創設。
また、地方と都内大学が単位互換制度による学生の交流促進事業や、地方へのサテライトキャンパス設置に関する調査研究及び都内学生が地方で就業体験するインターンシップのポータルサイトを拡充する事業も予定される。
そうした中、学部・学科の再編や学生の支援体制を見直し、経営の効率化など様々な改革を打ち出し、18歳人口が再び減り始める「2018年問題」を前に、「少子化・グローバル化」へ取り組む大学トップによるシンポジウムが行われ参加してきました。
東京工業大学は「2030年世界トップ10に入るリサーチユニバーシティ」を目指し、世界レベルの研究者・リーダーを輩出するグローバル化、研究成果の社会還元・国際貢献、研究力の強化とイノベーション創出を掲げ、一昨年から「学院制」のもと6学院・19系・1専門職学位課程へ移行。津田塾大学では今年度から創始者の理念を継承し、「《変革を担う、女性》の持続的研鑽を生涯にわたり支える」とのビジョンを策定し、「2050年までにpublic service分野での女性参画50%」を実現する学生輩出へ、渋谷に総合政策部を開設した。「実践的な英語」「ソーシャル・サイエンス」「データ・サイエンス」の3つの基礎科目を、企業や官庁からの講師やフィールドワークにより課題解決方法など学ぶ。
立教大学においては「スーパーグローバル大学創生支援」により5年間で海外協定を50校増の183大学、日本人学生の留学経験者数約1.5倍の946人、全学生に占める外国人留学生は345人増で989人に上る。
学生を受け入れる産業界から松本晃カルビー(株)会長兼CEOが、組織を動かすリーダーシップ・次世代リーダーの育成など幅広い経験を披露。自身の経営理念とする「取引先、社員・家族、コミィニティ、株主から尊敬・称賛・求められる会社」とすべく、組織の仕組みや環境、制度及び文化を変革し、“ダイバーシティ”“働き方改革”を重視。
社員や上司、企業人として求める要素や姿勢など、ユーモア溢れるトークで会場を沸かせた。
何れのシンポジウム登壇者も専門知識に止まることなく、幅広い一般教養、「リベラルアーツ」を身に付けた人材であることを期待している。