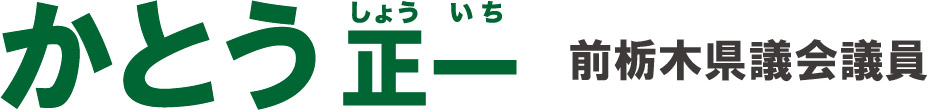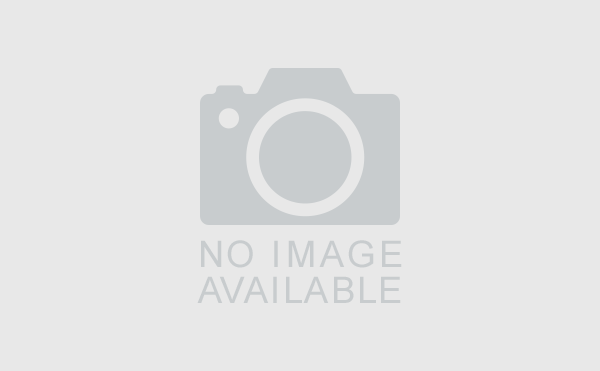とちぎのものづくりを進める上で、産業集積など本県の強みを活かし重点的に振興を図るため、県では《自動車・航空宇宙・医療機器・環境・光》といった5分野を特定し、総合的な支援を行い本県産業の競争力強化と、県内中小企業及び地域経済の活性化に取組んでいる。
先般、本県の自動車産業を牽引する企業である日産自動車(株)栃木工場(上三川町)を、同労組出身・神藤昭彦町議の仲介により県内地方議員とともに訪問した。合わせて、日産自動車開発の《ニューモビリティカー》を公用車へ試験導入する上三川町も調査。
神藤町議進行のもと、中村栃木工場長・星野上三川町長からの歓迎挨拶に続き、中村工場長より事業所概要を説明頂いた。エンジン製造2か所、車両工場を3カ所国内展開し、本工場は1968年鋳造部品の生産開始以降、71年に組立工場が完成した。
現在ではシーマ・フーガ・スカイラインなど9車種の高級車やスポーツカーを国内外向けに生産。敷地約2,922,000㎡と国内工場最大の面積には、全長6.5㎞の高速耐久テストコースほか様々な環境・条件を想定したテストコースを有す。従業員数約5,300人、平均年齢42.6歳であり、工場部門は平均勤務年数22.7年の熟練技術者達が年間約25万台の生産能力を支える。
日産自動車は高齢者・単身者世帯の増加や乗用車の近距離移動・少人数乗車の使用実態、低炭素社会の実現に資する環境対応車によるコンパクトなまちづくりに適した交通手段に着目し、超小型モビリティの実証事業に取組む。超小型モビリティは原付以上、軽自動車未満の新しいカテゴリーの乗り物です。コンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ身近な移動手段の1~2乗り車両。
上三川町は昨年6月より日産自動車協力で、リースにより公用車へ試験導入。町は軽自動車8台含め33台公用車を保有する一方、原付バイクは職員が利用経験に乏しいことを重視。従来の公用車利用は年間約5,600回、1回平均走行距離は約25km、約7割は1人での乗車実績であった。モビリティカー導入から今年3月まで利用は119回、平均走行距離約7㎞で施設調査や資料搬送の利用が多かった。課題として「荷物積載量が少ない」「後部座席が狭い」「エアコンがない」など原付バイク同様の指摘に加え、「後方が後退時見づらい」「軽自動車より安価な保険料」といった改善点が提起。
報告を基に私から、公道走行に際し道路運送車両法に基づく国交省認定を要することから、職員への運転講習の実施や受講状況、リース事業導入経費や事業への国等支援の有無等伺った。
町では引続き検証が必要とのことから、今年度も継続実施することとした。