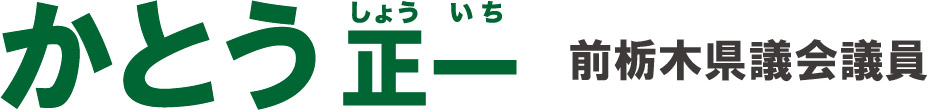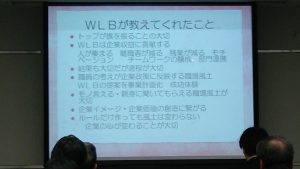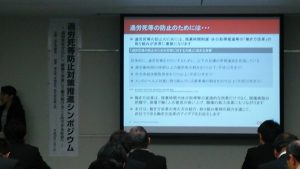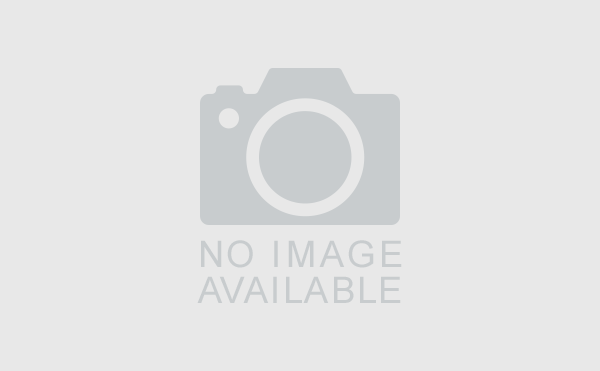今年10月に発表された「過労死防止対策白書」によると、週労働時間が60時間以上の雇用者は20%以上に上り、パートタイムを除く一般労働者の年間総労働時間は平成5年以降も2,000時間前後で高止まりしている。一方、有給休暇の取得率は5割を下回る水準で推移。
県内30人以上の事業所における労働者の1人平均年間総実労働時間は、前年対比で9時間減少したものの1,843時間であり、全国平均1,785時間より58時間長いという状況にあります。建設業が最も長く2,189時間、次いで運輸・郵便業2,062時間、製造業1,947時間となっている。片や宿泊・飲食サービス業が最も短く1,313時間であり、それに卸売・小売業1,638時間、医療・福祉業1,733時間と続く。 業種別に全国比較すると、県内建設業が108時間長く、医療・福祉業は12時間、運輸・郵便業で8時間長いとされ、金融・保険業は全国より42時間短い。
これら本県労働時間の状況に対し栃木労働局では、昨年「過重労働解消」として74事業場の監督指導を実施。その内、58事業場に労働基準関係法令違反があり、36事業場は【違法な時間外労働】で「月80時間を超え100時間以下」が10、「100時間超」は8事業場、【賃金不払残業】9、過重労働への【健康障害防止措置】に関しては16事業場が未実施だった。
そうした中、過労死等による労災請求件数は、平成23年度から「脳・心臓疾患」「精神障害」それぞれ6~9件で推移。業種別で「製造業」、年齢別では「50代」が一番です。
国では平成26年11月「過労死等防止対策推進法」が施行され、事業場への監督指導は元より、改善取組みの助言も行っている。
今月7日(月)とちぎ福祉プラザを会場に厚労省主催のシンポジウムが開催され、医療法人社団亮仁会 那須中央病院及び村田発條(株)が取組む実践例報告、三菱UFJリサーチ&コンサルティング天野さやか氏による「働き方改革」基調講演等行われ参加してきました。
その際、自身の過重労働による健康障害・失業経験、過労死した家族・友人を持つ家族の会の方達から伺った体験談は、深い悲しみと助けられなかった事への後悔・苦悩、過重労働を強いた会社への強い怒りと労災認定に向けた高い壁・・・。大切な人を突然失った悲劇は、その後も「なぜ、どうして」と家族は問い続けています。
体験者から「何のために働くのか、働くこととは人が幸せになるためにある筈」、「働くことを通じ、夢を抱いて明るく生活できる社会であってほしい」との切実な思いが語られた。