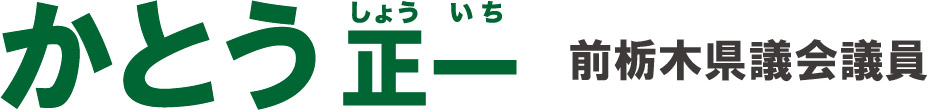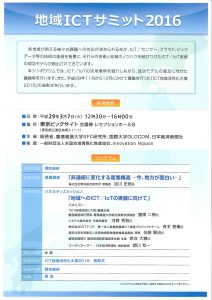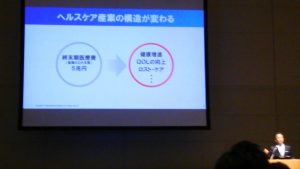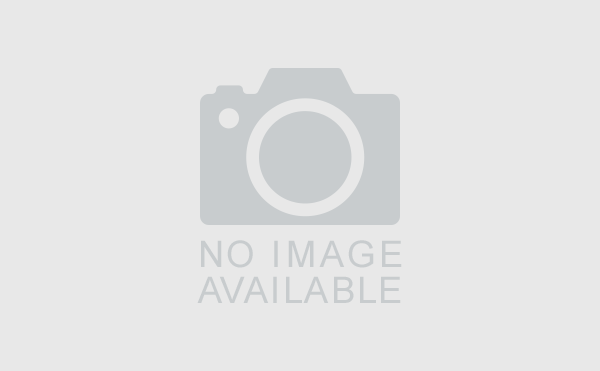総務省は7日(火)東京ビックサイトにおいて、地方が抱える人口減少・少子高齢化による労働力不足や地域経済の衰退、或いは災害対応等様々な課題解決にIoT、ビックデータなどICT(information&communication technology「情報通信技術」)を活用した優れた取組み「地域活性化大賞」表彰式を含む地域ICTサミットを開催。(株)野村総合研究所谷川史郎理事長の「非連続に変化する産業構造―今、地方が面白い―」とした基調講演に続き、表彰審査会長で慶応大学総合政策部圀領二郎教授や受賞団体代表によるパネルディスカッションも行われ、ICT活用の可能性や実用化までの経緯・課題等各々の取組が紹介された。
谷川理事長から「失われた20年での地方の状況」「1995年を境に先進国でも珍しい労働力不足の加速」に加え、日本経済の7割を「内需」が支える現状に触れる一方、飛躍的な産業技術の進展が一部の大手企業や都市でしか生かされず、「失敗のリスクが低く抑えられる地方や中小企業だからこそ、ICT活用によって新業態が生まれやすい」と強調。
鹿児島市内の空き店舗による全自動コインランドリーや佐賀県嬉野市農家の大学と連携した農作物の栽培・品質管理の自動化事業とともに、会津若松市データバレー、飯田市航空宇宙部品産業クラスター構想といった自治体の取組みも報告された。
パネルディスカッションでは医療・介護資源が乏しい離島での患者の複数疾患管理や多職種が携わる高齢者への対応に、電子カルテに頼らず施設間を双方向で情報共有するネットワークシステム構築に取組んだ佐渡市地域医療団体から「離島ならではの必然性の一方、知識・取組方法ゼロからのスタート」であったこと、道路情報をリアルタイムでオープンデータ化した静岡市では「人事異動で継続したICT活用体制維持の難しさ」を指摘。
システム作りの通信事業社からは自治体同士でもシステムメニューの違いから、「何れもオリジナルとなり、プログラムの共通化・汎用性が図れない」との意見も示された。
今回のICT活用事例の募集には全国から104件寄せられ、縫製工場の余剰リソースを活用し、全国のアパレル事業者・メーカーからの生産受注マッチングシステムを開発した熊本市シタテル(株)の総務大臣賞初め、優秀賞・奨励賞など12団体が受賞。
本県でも2020年までの5か年を期間とする「とちぎICT推進プラン」を策定し、県民の利便性向上と活力の創造、行政運営の効率化・情報セキュリティ対策、災害時でのシステム運用に取組んでいます。