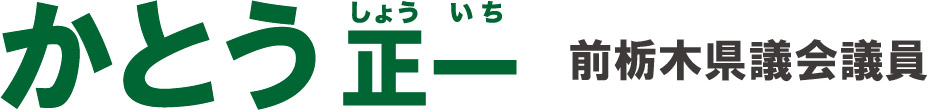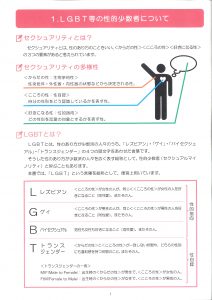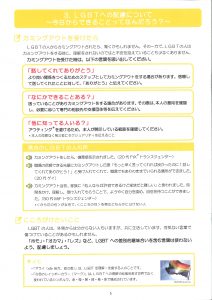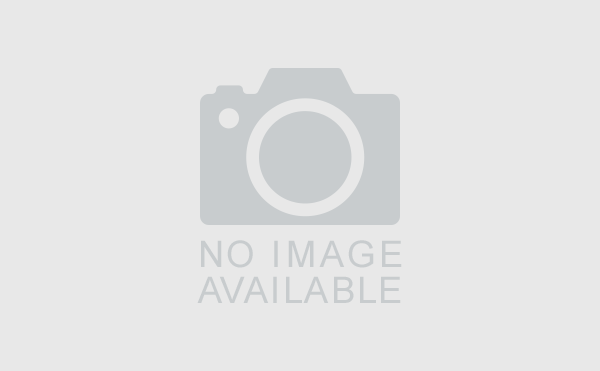3月末告示された新学習指導要領は、小中学校体育における「思春期の性」に関する記述を従来通りの内容とした。文部科学省が指導要領改訂に際し、昨年募集したパブリックコメントには「多様な性」についての言及を望む意見が全体の12%、約370件寄せられた。
朝日新聞の取材でスポーツ庁は、「LGBTについて小中学校段階でうかつに教えると、いじめにあう恐れがあり教師の指導の仕方も難しい」とのコメントの一方、今年度から使用される高校家庭科教科書に、初めて「LGBT」という表現が掲載されるなど改善も。民間調査では、13人に1人の割合でLGBTの人がいるとの報告があります。
私は今年に入って早々、ある若者の訪問を受け、自身で作成したレポートを渡されました。
20代前半の「彼」は小学校低学年で、自身の性への違和感を感じ始めたそうです。両親が楽しみに用意してくれた女の子の服装と赤いランドセル、学校でのトイレ・・・。
同性の同級生と少し異なる自らの感性に、子どもながら「自分は病気なのか」「自分は普通じゃない?」と自身の存在を問い続け不登校となるものの、高校では学校の理解のもと通学することが出来ました。しかし、未だ理解が不十分な社会にあって、継続かつ安定的な就労に就くことは困難です。
県ではこれまでも教育現場において、一昨年の「性同一性障害に係る児童等に対する対応の実施」に関する文科省通知や、昨年配布の周知資料を基に支援や配慮に努めるとともに、性的マイノリティに関する講演会や人権教育校内研修等も取組んでいます。
一方、国家公務員の就労ルールを定める人事院は、今年1月規則の運用通知を改め、「性的指向と性自任」をからかったり、いじめの対象にしたりする言動をセクハラとし、懲戒処分の対象と明記。厚労省がわいせつな言動を念頭にセクハラを定義する民間企業向け指針より、厳格なルールを課したことは性的マイノリティーへの理解を、より進めるための対応と考えます。
国内でも渋谷区による同性婚への証明書発行や大阪市での同性婚カップルへの里親認定がされる一方、LGBTへの寛容さを示していたトランプ大統領は今年2月、トランスジェンダーの生徒らによる学校トイレの使用に関するオバマ前政権の通達を撤回。
私は新年度人権施策に関する予算質疑を委員会にて、「人権施策推進基本計画」や「男女共同参画プラン」、「青少年プラン」ではLGBTにおける取組みが「その他の人権」という内容でわずかな記述に止まることや、先の新学習指導要領や人事院の対応、群馬県が1月作成した冊子等紹介し、今後の本県における「ダイバーシティ社会」の一層の推進に向け提言したところです。